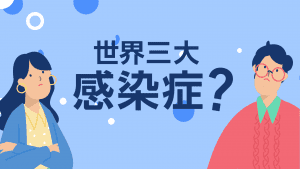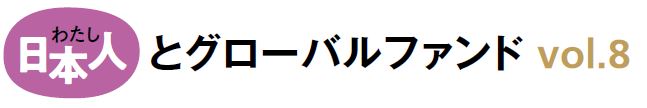
小さな蚊が見せてくれた、大きくて広い国際医療の世界
インタビュー
狩野繁之氏(国立研究開発法人国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部部長、グローバルファンド技術審査委員会(TRP)メンバー)
長年にわたってマラリアの研究に尽力され、2017年からはグローバルファンド技術審査委員会(TRP)のメンバーとして活躍される狩野繁之さん(国立研究開発法人 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部 部長)に、マラリアの研究や対策に携わるようになったきっかけ、研究のため訪れたアフリカやアジアの国々での思い出、TRPメンバーとしての活動について、お話を伺いました。
恩師の導きで、マラリア一筋に歩んできた
― 先生の医学生時代にもおそらく過去の病気であったマラリア。それにかかわるようになったいきさつはなんでしょう。
私はカトリックですが、医学生(群馬大学)の時代、教会の関係で韓国のハンセン病療養所で医療奉仕をしたり、地元の草津温泉にある国立療養所(栗生楽泉園)にも教会の関係でお手伝いに行きました。そんな経験から、ハンセン病にかかわることが信仰に生きることになる、と当時は思いました。いまはそんな純粋な自分がいたことも思い出せないけれど(笑)。卒業後はハンセン病や熱帯病、そうでなければ途上国の健康増進のために外科や産婦人科を専攻して、国際協力的な仕事を医師としてやりたいと思っていました。

それで熱帯医学を専門とする鈴木守教授のもとへ相談に行ったら、「おまえの一番いいようにしてやる。ついてこい」と。先生はマラリアの専門家で、まず「基礎研究をやれ」。自分は患者支援をしたいですと言ったら、先生が「そんなものは年取ればいくらでもできるから、いまは基礎だ」(笑)。当時、分子生物学が始まって、新しいことばかり。これはすごいと思って、マラリアのDNA検査、簡易PCR検査なんて、僕がはじめてやったんです。博士論文のテーマも、マラリアワクチンの候補抗原、そのタンパク質の配列を決めるといったもので、いまなら高校の夏休みの課題程度ですよ(笑)。
そういう研究をしながら先生のお供でアフリカのスーダンへ通いました。スーダンでは1970年代に日本が農業援助で砂漠地帯に灌漑用水を引き、そのため蚊の発生環境ができてマラリアが増えた。日本は環境も考えず無知で開発をした、これはマン・メイド・マラリアだと世界で非難された。そこでマラリア対策にも入ったのです。顕微鏡や殺虫剤、蚊帳を持ち込んだのが最初の仕事で、JICAから委託を受けた鈴木教授を手伝いました。しかし、机上で考えたようにいくものではなく、地平線まで用水路が流れていくスーダンの大地でどう対策したらいいのか、絶望的な気持ちになったものです。でも、そのころからマラリアを一生の仕事にしようと思いました。
― 恩師の鈴木教授の影響は大きかったようですね。
先生は日本ではじめてマラリア原虫の培養に成功するなどマラリア研究の第一人者で、のちに医学部長や学長も務めました。世界の流行地と日本を行き来しながら、フィールド対策に生かせる研究をつねに心がけていました。現地へ持っていけるような検査法の開発とか、フィールド疫学の評価研究とかをやりなさい、と私にも指導された。私は現職の国立国際医療研究センター研究所には20年前に異動してきましたが、ここは海外での対策研究が専らで、かつての先生の教えが役に立っています。
教授とともに行ったのはスーダンのほか、アマゾン、フィリピン、ソロモン諸島……。日本にマラリア対策をやる人など当時はいないものですから、みな群馬大学に話がきて、先生が忙しければ私がかわりに行くこともありました。依頼元に「専門家を呼んだのに学生が来るとはなにごとだ」と怒られて、先生が「彼はもう4年もやっているし、マラリアで彼以上に知っているやつはいない」と言ってくれたこともあります。
国内でマラリアは50年代末には終息していたし、日本はもともと寄生虫の研究には熱心で、早めに駆除が終わりました。にもかかわらず、マラリアの研究を続けていたのはーーしかも群馬の田舎でというと語弊がありますがーー凄いと思います。鈴木先生はリバプールの熱帯医学研究所に留学経験があり、世界に目が向いていたのでしょうね。私も先生に感化され、さいわい世界の各地に行かせてもらい、だんだんと自分の「敵」が巨大であることに気づいていきました。
広大なスーダン、医療と隔絶されたアマゾンの森林、島々が点在するソロモン、みんな大変でしたし、タイやミャンマーの国境付近では政治対立もあって行動も制限。住民参加型の対策なんて言ったとたんに軍政への不穏な動きとして警戒され、ずっと監視役がつきました。社会も気候も環境も違い、蚊の種類や原虫も違う。どこにどう介入するのがいいか、一つひとつが応用問題を解いていくような感じでした。
そうそう、そうやって現地へ通い、現地からも大学へ留学生を迎えるなかで、英語も身についっていったといえるでしょう。
― 現地での対策の経験で、いまも印象深いものはありますか。
いちばんおもしろかったのは、フィリピン・パラワン島でのマラリア対策でしょうか。ちょうど政府主導の垂直型から、住民参加型の水平型に移ってきたころで、群馬大学に留学していた人がフィリピン大学の教授になっていた縁から現地のNGOリーダーともつながり、ある村に顕微鏡を入れて診断と治療を始め、蚊帳を吊ることを教え、みんなで草を刈ってボウフラ退治をし、取り組みを始めました。
そのころ石油会社のシェルがパラワン島沖で天然ガスを掘り当てたらしく、われわれに近づいてきまして、「シェルは石油を掘りにきたのではない、夢を掘りにきたのです。林業、水産業、保健の分野で資金を提供する用意があります」なんて言うものですから(笑)、では手伝ってくれ、と。パラワン島全体にある344か所の診療ポストの全部に顕微鏡を提供してくれました。われわれも各村の村長に責任の持てる人を送ってくれ、検査技師の養成をするから、とお願いしたら、送ってきたのはどの村もみんな女性です。男は働かない(笑)。彼女たちは7週間缶詰でトレーニングを受け、終了後には顕微鏡をもって村へ帰りました。その滞在費も食費もシェルが出してくれた。そうやって2年がかりで344か所に検査スポットを整備し、女性パワーとコミュニティパワーを活用して年々、検査率があがり、いったんマラリア患者数の報告は増えますがやがて減少に転じ、死亡者も減ってきました。
そのうち顕微鏡が壊れてきたので、あらためてグローバルファンドに助成金を申請し、総合的なヘルスシステムを構築し、検査技師たちのルートで情報も集まってサーベイランスもでき、2030年までにはマラリアの死亡者をゼロにする見込みです。この経験を周囲の島でも普及させているところですが、こうしてグローバルファンドのお金を使わせてもらった私が、のちにグローバルファンドの審査委員となって世界から寄せられた申請書を審査するというのも、感慨深いものがありますね。
グローバルファンド審査委員として
―そのグローバルファンドの審査委員は、どのくらいお務めなんでしょうか。
2017年から今年まで4年間ですが、これも僕の意思ではありません(笑)。外務省のかたから電話がかかってきました。日本はグローバルファンドの拠出金は世界5位なのに、いま審査委員に日本人がだれもいない。厚労省から、医療センターからあなたを紹介された、応募していただけますか、と。これまで審査委員を務めた井戸田一朗先生も永井真理子先生もよく知っている間柄なので聞いたら、みな口を揃えて「大変ですよ。ひどい目にあいます」とおどかされました(笑)。最終的には採用されることとなりました。
審査の会合は年に3回ほどありますが、ジュネーブへまで行ったのは最初の1回で、そのときはマラリアだけで40課題ぐらいあり、11泊もして本当に大変でした。現在マラリアの申請も減ったのか、私はリモートでやらせてもらっています。
でも、初めてのときはもともと大変と聞いていますし、初日に空港横のホテルに缶詰にされて、「あなたがたはスイスのきれいな空気を吸いにきたのではありません。終わるまで一歩もホテルを出ないでください」と釘を刺されました。朝昼晩と食事はよくて、食べすぎ飲みすぎに苦労しましたが、目の前に課題は山積みです。申請書を読み、翌日カントリーチームの人にヒアリングし、他の審査委員と議論して、そこまではいいんですが、その結果を当日中に報告書に書くのが一苦労。当日というのは午前2時でして(笑)、それが終わって自分の翌日分を読まなきゃいけないのにはネを上げましたね。英語ネイティブの人は余裕があるのか、夕飯もゆっくり食ってワインも飲んで、そのあとしゃべったりしているけど、こっちは付き合ってるわけにもいきません。
二、三日過ぎたころ、僕の担当のスタッフに、「仕事量が多くて時間がないんだが、箇条書きでいいかな」と言うと、「ええ、箇条書きでけっこうです」と。それでポイントのメモを渡すと翌朝にはフルセンテンスのレポートに仕上げておいてくれるんです。ああ、秘書はこうやって使うのか、と悟りました。
全部終わった日にみんなでレマン湖に行って、レストランを借り切って打ち上げをしてくれたのは楽しかった。そしてホテルに帰ってきて、「そうだ、ここにはカジノがあった。話のタネに一度行くか」と部屋を出たところを同僚に見つかりましてね。「カジノへ行く? カード持ってるのか? ダメだ。おまえは毎日、何百億のカネを扱ってきたろう。1万ドル、2万ドルははした金に見える。全部置いて100ドルだけ持っていけ」と言われました。そうかと思ってカードも財布もおいて、100ドル札だけ握りしめてカジノに降りていって、数秒で終わりましたよ(爆笑)。たしかにラウンド中に金銭感覚はなくなってきますね。
― それは貴重なご経験でしたね(笑)。審査の現場はいかがでしたか。
世界各地からの申請には、その土地ならではのバラエティある挑戦が盛り込まれていて、感染症対策の幹というか王道的なものと、周辺のそうしたもやもやしたプロジェクトとが相まって、その土地なりの特色ある対策が構成されています。だけど審査委員は削るのが仕事、ひどいときには6割ぐらいに減らしてくれと言われると、そういう枝葉のもやもやした部分ーー本当はそこがいちばん大事なのにーーが切られ、幹だけが残ることになる。モンブランの登山は一本道で、そのコストエフェクティブな登り方を考えよ、というわけです。そのへんが、米国のPMI(米大統領マラリアイニシアチブ)などと比べて残念ですね。もっともっとお金が集まれば、カスタムメイドな対策をさせてあげられるのですが……。
― グローバルファンドの審査委員に日本人がかかわることについては、どう感じておられるでしょうか。
審査は公正公平といいつつ、各国から送り込まれてくる審査委員には、自国の資材やモノが動くようなプロジェクトの採択を期待されている面もあるようです。でも、現場では自分が何国人ということを思い出すひまもないぐらい必死に審査書類を読み、自分の能力や経験をフルに生かして検討し、議論します。そうすると、委員のあいだにおなじ目的のために戦っている同志という連帯感が高まってくるんですね。世界のマラリア対策を少しでもよくするために結集した集団で、崇高な使命感に包まれる気がしました。議事を終えたときの高揚感や、打ち上げのパーティーで飲んだ酒は忘れられない、幸福な経験です。今年、日本から新しい審査委員が2名、採用されたようですが、なかなか経験できない機会ですから、心からエールを送りたいですね。
今年(2020年)も3度の審査会の案内が来ており、リモートだとは思いますが、それでも実際にどこで呼び出すかわからないから予定は空けておくようにと言われています。気持ちのうえでは呼ばれないと助かるような、でも呼ばれてまたあの場に参加したいような、複雑な気持ちです。
国際医療、国際貢献に、いま日本人として考えること
―グローバルファンド、ひいては国際保健に日本はなにができるでしょうか。
国際機関で働く若い人をもっともっと増やさないといけないですね。いまや若い人には、物怖じしない人や語学が堪能な人も多い。国際機関で働く人材が増えてくると、そこに日本人のエッセンスのようなものが加味されて、日本人として言うのはおこがましいですが、ある意味「正しい」国際感染症対策だったり難民対策だったりができるような気がします。
この「正しい」とは、海外の政府系援助のように自国益優先ではないということです。青年海外協力隊に多くの人が参加していますが、みな現地の人に溶け込み、現地の人のためになにができるかを考え、現地の人から感謝され、惜しまれながら帰国しています。マラリア対策でも、ラオスにそんな人が派遣されてきています。

そうすると日本という国の評価も高くなる。ああいう国になりたいと思われたり、日本のファンになってくれる人も増え、国際協力においても特別な位置がとれるようになるのだと思います。日本の政治家には国益を語って、たとえばフィリピン沖のシーレーンを確保するために現地に支援をするのだ、マラリアが増えようが減ろうが関係ないんだと口にする人も見たことがあり、若いころの私は、そういう言い方はないじゃないかと内心憤ったこともあります。政治家にももちろん考えがあるのでしょうが、僕ら現場で医療者として、あるいはグローバルファンドの審査委員として働いたときも、政治的な思惑や国益は関係なくやってきました。現地の人のためというマインドで働けば、おのずと日本へも高い評価を得られるような気がします。それこそが真の「情けは人のためならず」でしょう。
― そうした人を増やすにはどうすればいいのでしょう。
一朝一夕には難しいし、若者の留学離れ、内向き志向も言われます。いまは私の後進を発掘しようと、熱帯医学会などで学生の人材育成に取り組んでいるところです。昔、自分が釣られたように、若い純粋そうなやつを一本釣りしてやろう、と(笑)。

技術面でも、日本にはもっと世界で応用できるものがいっぱいあります。マラリアの診断機器にもすぐれたものがあり、顕微鏡検査技師が30分かかるところを1分で判定でき、その感度もすごくいいものを日本は開発していながら、販路で遅れをとっている。薬も抗生物質などいっぱいあるけど、外国で販売するのが難しい。
機器でも製薬でも高いテクノロジーがあるのに、世界の一線へ出すあと一歩の能力がないのです。GHIT Fund(グローバルヘルス技術振興基金)などができ、応援してくれる体制も整ってきてはいます。国立国際医療研究センターでも外国の流行地の研究所や大学とMOU(包括的共同研究協定)を結んで、海外の患者さんたちに治験の協力者になってもらって、一緒に臨床研究できるようなシステムを開発したりしています。本当にいいところへ来ているんだけど、最後、人材だったり、国際的なところへ応用する覚悟や戦略だったりが足りないんです。若い人には、そういうことに勇気をもって挑戦してほしいものです。
インタビュアー
FGFJ レポート編集協力エディター
永易 至文
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
BACK NUMBER
グローバルファンド日本委員会(FGFJ)では、グローバルファンドと何らかの関わりのある日本人をインタビューし、「日本人(わたし)とグローバルファンド」というコラムでウェブサイトに掲載しています。バックナンバーはこちらのページからご覧ください。