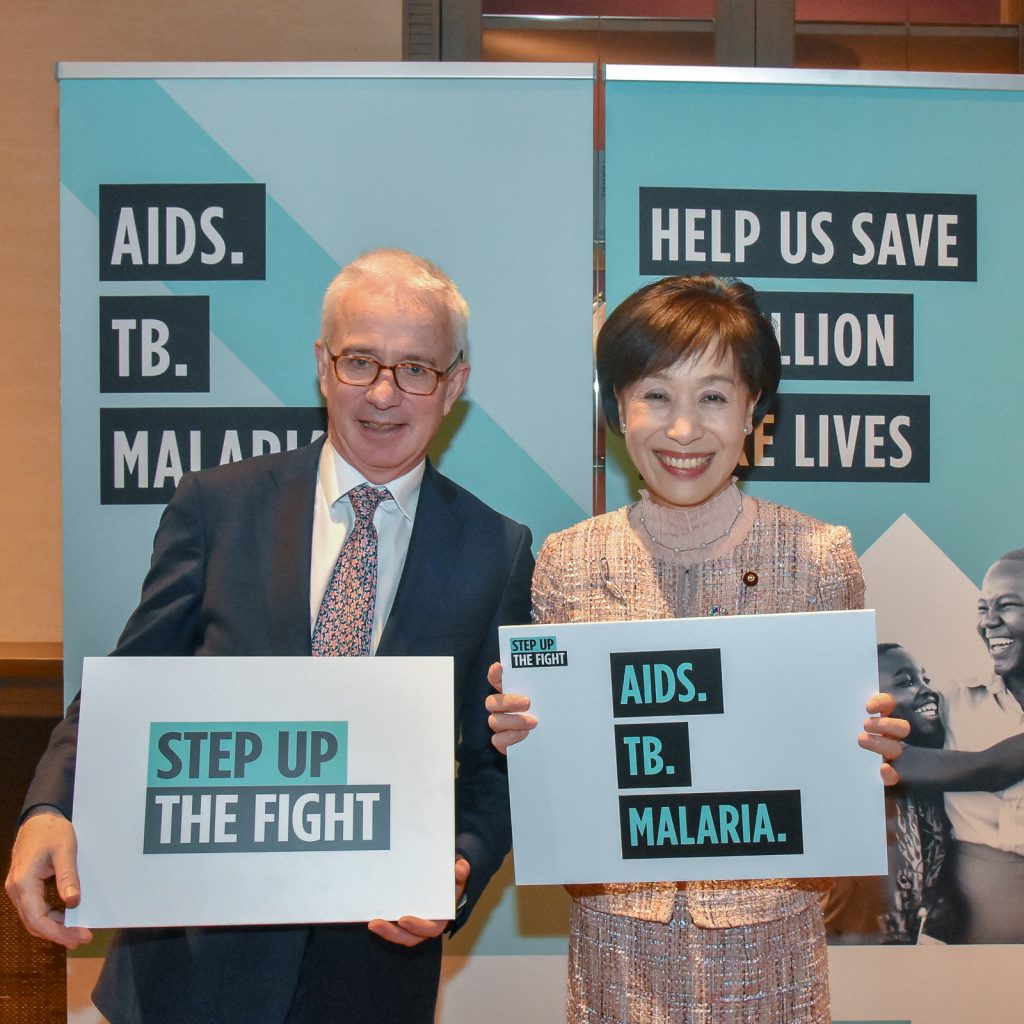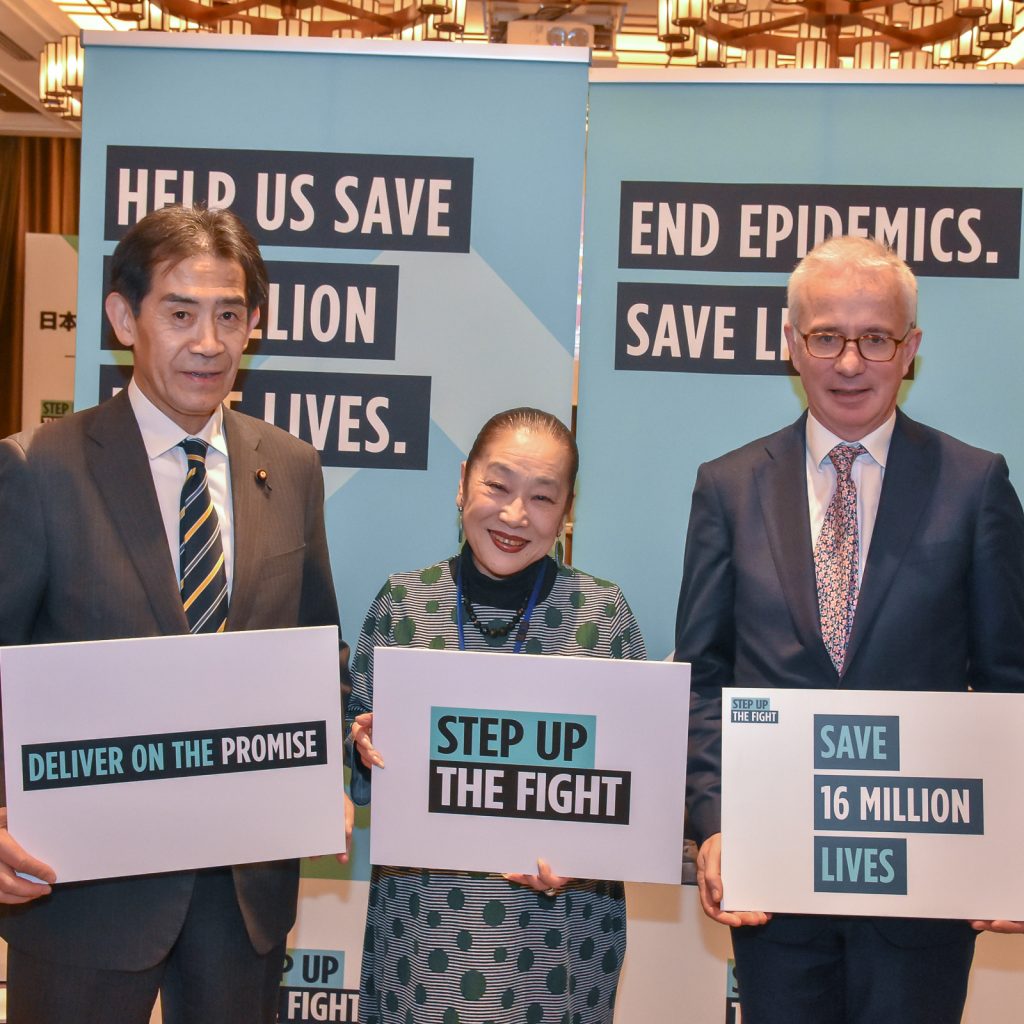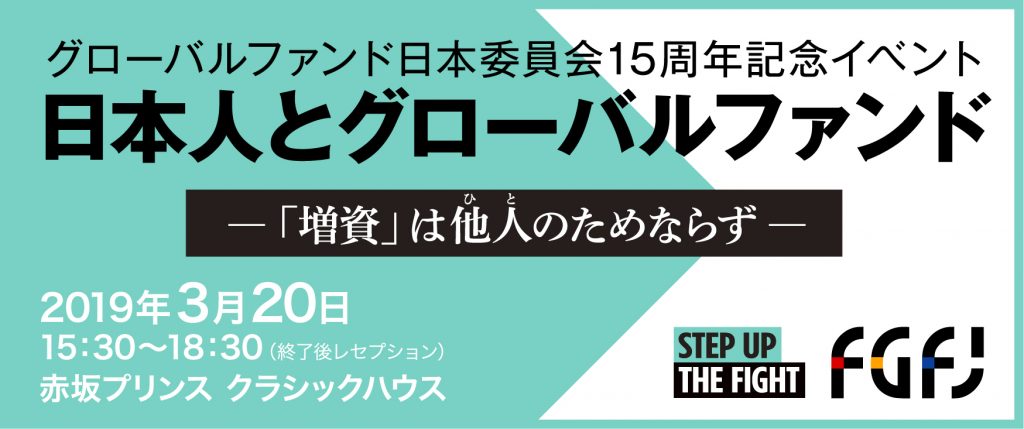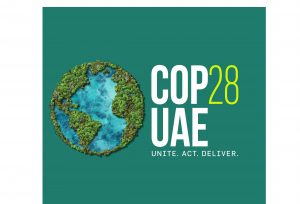(公財)日本国際交流センター(JCIE)/グローバルファンド日本委員会(FGFJ)は、2019年3月20日、グローバルファンド日本委員会の発足から15周年を記念したイベント「日本人とグローバルファンドー増資は他人のためならずー」を開催しました。
(公財)日本国際交流センター(JCIE)/グローバルファンド日本委員会(FGFJ)は、2019年3月20日、グローバルファンド日本委員会の発足から15周年を記念したイベント「日本人とグローバルファンドー増資は他人のためならずー」を開催しました。
グローバルファンドのピーター・サンズ事務局長をはじめ、日本の国会議員、外務省・厚生労働省の関係者、保健医療分野の専門家、感染症の当事者を含む市民社会、民間企業、国際機関の代表など国内外から約150名のご参加を得て、15周年を祝うことができました。日本委員会の15周年は偶然にもグローバルファンドの第6次増資の年と重なったことから、このイベントは増資をテーマにとりあげ、なぜ日本がグローバルファンドに資金を出すのか、納税者として一人ひとりに考えていただく機会となりました。
2004年、新たな外交課題“感染症”へのオールジャパンの対応として誕生
 開会にあたりJCIEの大河原昭夫理事長は、2004年にグローバルファンド日本委員会を立ち上げた最初のきっかけは日米関係の一端からもたらされた、というエピソードを紹介し、感染症という新たな外交課題に日本がオールジャパンで貢献できるよう基盤を作りたいという思いから日本委員会が設立され、現在世界に4つあるフレンズ・オブ・ザ・グローバルファンドの第1号となったと述べました。JCIE理事長として各界の関係者のこれまでのご協力に感謝するとともに、15周年の節目は、2030年の持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた新たなスタートでもあると述べ、三大感染症の流行の終息のために日本がより大きな役割を果たせるよう努力していきたいと決意を新たにしました。
開会にあたりJCIEの大河原昭夫理事長は、2004年にグローバルファンド日本委員会を立ち上げた最初のきっかけは日米関係の一端からもたらされた、というエピソードを紹介し、感染症という新たな外交課題に日本がオールジャパンで貢献できるよう基盤を作りたいという思いから日本委員会が設立され、現在世界に4つあるフレンズ・オブ・ザ・グローバルファンドの第1号となったと述べました。JCIE理事長として各界の関係者のこれまでのご協力に感謝するとともに、15周年の節目は、2030年の持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた新たなスタートでもあると述べ、三大感染症の流行の終息のために日本がより大きな役割を果たせるよう努力していきたいと決意を新たにしました。
三大感染症への取り組みは将来への投資である
 鈴木憲和外務大臣政務官は、ご挨拶の中で、世界で今なお多くの尊い命を奪っている三大感染症は、貧困と深く関係し、各国の活力や経済成長の源も損なうものであると述べ、SDGsの理念である「誰一人取り残さない社会」の実現を図る上で、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)は不可欠な要素であり、日本にとって三大感染症対策とグローバルファンドへの貢献はその一環であると強調しました。そもそも日本は、2000年のG8九州・沖縄サミットで感染症対策を主要課題として取り上げ、追加的資金調達の必要性を各国とともに確認した。このことがグローバルファンド設立の発端となったと述べ、日本が果たした重要な役割に言及しました。
鈴木憲和外務大臣政務官は、ご挨拶の中で、世界で今なお多くの尊い命を奪っている三大感染症は、貧困と深く関係し、各国の活力や経済成長の源も損なうものであると述べ、SDGsの理念である「誰一人取り残さない社会」の実現を図る上で、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)は不可欠な要素であり、日本にとって三大感染症対策とグローバルファンドへの貢献はその一環であると強調しました。そもそも日本は、2000年のG8九州・沖縄サミットで感染症対策を主要課題として取り上げ、追加的資金調達の必要性を各国とともに確認した。このことがグローバルファンド設立の発端となったと述べ、日本が果たした重要な役割に言及しました。
さらに鈴木政務官は、民間での外交対話を担ってきた日本国際交流センターの尽力によってグローバルファンド日本委員会が発足して以来、15年の間に各界の有識者の参加を得て行われた様々な活動に敬意を表すとともに、その活動が感染症対策における日本の官民協力の促進と日本の国際貢献に繋がってきていることを誇りに思うと述べ、「三大感染症への取組みは、世界の将来への投資である。国会議員の一人として国民の皆様の理解が得られるよう努力していきたい」と結びました。
第6次増資計画:140億ドル以上の調達を目標
 グローバルファンドのピーター・サンズ事務局長は基調講演を行い、G8九州・沖縄サミット以来の日本のグローバルファンドへの貢献や国際保健分野でのリーダーシップを称え、また官民パートナーシップでそれを支えてきたグローバルファンド日本委員会の活動に謝意を表しました。またサンズ事務局長は、グローバルファンドと世界中のパートナーの努力の結果、2002年設立以来三大感染症による死者数はほぼ半減したことを挙げ、これは大きな成果である一方、それでも毎年約250万人が、予防・治療できる病気で命を落としていることに、我々はもっと緊迫感を持たなくてはならないと警鐘を鳴らしました。現状レベルの対策を維持しているままでは、死者数は再び増大し、世界保健機関(WHO)や国連合同エイズ計画(UNAIDS)などの技術パートナーが制定した、2030年にエイズ・結核・マラリアの流行を終息させるという目標に向けた軌道に乗ることができないとし、そのために2020~23年の3年間にグローバルファンドが調達すべき額は140億㌦であり、感染症との闘いを強化(step up) しなければいけないと結びました。
グローバルファンドのピーター・サンズ事務局長は基調講演を行い、G8九州・沖縄サミット以来の日本のグローバルファンドへの貢献や国際保健分野でのリーダーシップを称え、また官民パートナーシップでそれを支えてきたグローバルファンド日本委員会の活動に謝意を表しました。またサンズ事務局長は、グローバルファンドと世界中のパートナーの努力の結果、2002年設立以来三大感染症による死者数はほぼ半減したことを挙げ、これは大きな成果である一方、それでも毎年約250万人が、予防・治療できる病気で命を落としていることに、我々はもっと緊迫感を持たなくてはならないと警鐘を鳴らしました。現状レベルの対策を維持しているままでは、死者数は再び増大し、世界保健機関(WHO)や国連合同エイズ計画(UNAIDS)などの技術パートナーが制定した、2030年にエイズ・結核・マラリアの流行を終息させるという目標に向けた軌道に乗ることができないとし、そのために2020~23年の3年間にグローバルファンドが調達すべき額は140億㌦であり、感染症との闘いを強化(step up) しなければいけないと結びました。
プレゼンテーションの詳細は後日公開いたします。
「誰も取り残さない」感染症対策に不可欠なのは当事者の参画
 「感染症と闘うコミュニティ(当事者)の証言」のパネル・ディスカッションでは、結核に罹患し副作用で障害を負いつつアドボケートとして活躍するフィリピンの女性、HIV陽性者の世界的組織で活躍するインドネシアの男性に、ご自分のストーリーを語っていただくともとに、感染症との闘いの中で当事者が果たしてきた役割や、今後グローバルファンドとともに何ができるのか、米国法人日本国際交流センターの吉田智子のモデレートで議論しました。
「感染症と闘うコミュニティ(当事者)の証言」のパネル・ディスカッションでは、結核に罹患し副作用で障害を負いつつアドボケートとして活躍するフィリピンの女性、HIV陽性者の世界的組織で活躍するインドネシアの男性に、ご自分のストーリーを語っていただくともとに、感染症との闘いの中で当事者が果たしてきた役割や、今後グローバルファンドとともに何ができるのか、米国法人日本国際交流センターの吉田智子のモデレートで議論しました。
フィリピンのエロイザ(ルイ)・ゼペダ・テン氏は、多剤耐性結核にかかった体験をもとに、患者自身が病気と治療・副作用を理解し、障害者への差別をなくすために自ら立ち上がることの重要性を強調しました。
————————-
 “若き建築家として活動していた私は2006年末、繰り返しの高熱の末に倒れて病院に運ばれた。最初に運ばれた病院では全く原因が突き止められず、その次に行った病院でも誤診。その後、グローバルファンドの支援を受けた病院に運ばれて、ようやく結核性髄膜炎だと診断を受けた。しかし、やがて多剤耐性結核であることが発覚。闘病生活が長期化する中で、様々な副作用に苦しみ、視力も失っていった。
“若き建築家として活動していた私は2006年末、繰り返しの高熱の末に倒れて病院に運ばれた。最初に運ばれた病院では全く原因が突き止められず、その次に行った病院でも誤診。その後、グローバルファンドの支援を受けた病院に運ばれて、ようやく結核性髄膜炎だと診断を受けた。しかし、やがて多剤耐性結核であることが発覚。闘病生活が長期化する中で、様々な副作用に苦しみ、視力も失っていった。自暴自棄になっていたあるとき、自分より重い障害をもった人たちに出会い、自分の人生を受け入れる決断がついた。2013年にアクティビストとしての活動を開始。結核治療薬の誤った服用によって聴覚を失う患者は多く、そうした人たちのための結核障害委員会を立ち上げ、CKAT(結核アドボケーツ協議会) も設立し、結核に罹患した人々が受けている治療や副作用について正しく知ることを推進する活動を主導している。結核対策ではまだ医療の面が優先されていて、人権について語る機会が少ない。フィリピンでは、かつての大統領さえ結核で命を落としているにもかかわらず、未だに守秘義務が重要視され、結核に罹ったことを隠さなければならない。また、国民の2割は障害者であり、結核患者もその一部である。今後の取組みを前進させるためには、コミュニティのキャパシティ構築をし、人権に基づいた社会保障を整備していくことが極めて重要である。”
インドネシアのオマール・シャリフ氏(世界HIV陽性者ネットワーク(GNP+) プログラム・オフィサー)は、当事者を感染症対策の担い手とすることの重要性に理解を求めました。
 ——————————-
——————————-
“私は、薬物依存から一度回復し、海外に新しい職を得て心機一転新しい暮らしを始めた直後、在留資格を得るための検査でHIV感染が判明、即刻解雇、国外追放となった。HIVについて何の知識もなかった私は、ヘロイン使用を再開、2年間ホームレス生活を送った。そんな時、救いは、仲間のドラッグユーザーからやってきた。地元の大学とグローバルファンドの支援を受けたハームリダクション・プログラムがドラッグユーザー自身によって運営されていたのだ。清潔な針の必要性や代替薬物に関する指導を受けたのは初めてだった。私はコミュニティ・ミーティングに参加するようになり、やがて定期健診やHIV治療を開始することができた。そして、同じように苦しむ仲間への支援を拡げるために、インドネシアHIV陽性者ネットワークの設立にも加わり、次第にアジア地域やグローバルな活動にも関わるようになっていった。”
“エイズ対策には、当事者コミュニティが重要である。薬物使用者は、差別やスティグマを恐れるので、自ら公共サービスに出向くことはない。しかも、薬物使用者は早起きではないので、保健センターの9時~5時のサービスには誰も行かない。当事者の声を聞き、彼らの暮らしにあった対策を打つ必要がある。結核もエイズも、病気の社会的背景に対処しなければ、流行を終息させることはできない。一方で、国際支援から卒業する頃になると政府がまず予算から外そうとするのは、性産業従事者や薬物使用者、男性同性愛者などへのエイズ対策である。「誰一人とり残さない」というSDGsの取組みを前進させるためには、グローバルファンドがしっかりと卒業までの移行期を支えて、こうした人々を国が支援するルートを確保することが極めて重要だ。”
——————————
 稲場雅紀氏(アフリカ日本協議会国際保健部門ディレクター)は、1994年、横浜で開催されたエイズ国際会議の場にゲイ当事者として参加した当時を振り返り、高価な治療費を途上国の人々が支払うのは不可能、アフリカでは定時の薬の服用は不可能といった通説がまかり通っていた、そのブレイクスルーとして設立されたのがグローバルファンドだった、と述べました。2004年から09年までグローバルファンド理事会の先進国NGO代表団メンバーに加わった経験から、グローバルファンドでは、当事者が、理事会で各国政府代表と同じ議決権を持ち、国レベルでも計画策定や実施にかかわっていることを強調しました。また、資金の調達や使い道の意思決定に当事者が参画することの意義として、現場の感染症対策がより実効性の高いものになったこと、また、当事者側も強い覚悟を持つようになったことを上げ、「コミュニティは単に救われるだけの存在ではなく、自らを救ってきた。それが、グローバルファンドの17年間の歴史である」と結びました。
稲場雅紀氏(アフリカ日本協議会国際保健部門ディレクター)は、1994年、横浜で開催されたエイズ国際会議の場にゲイ当事者として参加した当時を振り返り、高価な治療費を途上国の人々が支払うのは不可能、アフリカでは定時の薬の服用は不可能といった通説がまかり通っていた、そのブレイクスルーとして設立されたのがグローバルファンドだった、と述べました。2004年から09年までグローバルファンド理事会の先進国NGO代表団メンバーに加わった経験から、グローバルファンドでは、当事者が、理事会で各国政府代表と同じ議決権を持ち、国レベルでも計画策定や実施にかかわっていることを強調しました。また、資金の調達や使い道の意思決定に当事者が参画することの意義として、現場の感染症対策がより実効性の高いものになったこと、また、当事者側も強い覚悟を持つようになったことを上げ、「コミュニティは単に救われるだけの存在ではなく、自らを救ってきた。それが、グローバルファンドの17年間の歴史である」と結びました。
様々な日本の組織がグローバルファンドと接点をもつ


続く「グローバルファンドのパートナーシップとSDGs」のパネルでは、グローバルファンドの國井戦略投資効果局長と、企業、メディア、財団など様々な立場からグローバルファンドと接点のある方をパネリストに迎え、日本国際交流センター執行理事の伊藤聡子(グローバルファンド日本委員会事務局長)のモデレートのもとでディスカッションを進めました。グローバルファンドは21世紀型官民連携基金といわれていますが、残念ながら、日本からそのパートナーシップの輪に入っている組織はあまり多くありません。今後、グローバルファンドが日本のアクターとどのようにかかわりをもっていくべきか、多くの示唆が得られた議論でした。
 冒頭、グローバルファンドの國井修局長は、パートナーシップの意義について、多くの組織は単独で仕事をしてその成果を独自にドナーに報告する方が楽であり、実は組織を超えたパートナーシップは口でいうほどたやすくはないとした上で、しかしこれを変えたのがエイズの流行だったと指摘しました。エイズの流行が一国の存在すら脅かすほど深刻であった2000年当時、各組織が個別に対応していてはとうていこの巨大な敵に太刀打ちできないと考えた当時のコフィ・アナン国連事務総長により、パートナーシップを促進するためのメカニズムの創設が提唱されたことがグローバルファンドの発端です。國井局長は、現在、グローバルファンドが支援する国では、「1つの予算、1つの計画、1つの報告」というルールのもと、その国の政府と様々な援助機関やNGO・市民社会が連携して対策を実施しており、グローバルファンドはそのための黒衣として促進・調整役に徹していることを強調しました。
冒頭、グローバルファンドの國井修局長は、パートナーシップの意義について、多くの組織は単独で仕事をしてその成果を独自にドナーに報告する方が楽であり、実は組織を超えたパートナーシップは口でいうほどたやすくはないとした上で、しかしこれを変えたのがエイズの流行だったと指摘しました。エイズの流行が一国の存在すら脅かすほど深刻であった2000年当時、各組織が個別に対応していてはとうていこの巨大な敵に太刀打ちできないと考えた当時のコフィ・アナン国連事務総長により、パートナーシップを促進するためのメカニズムの創設が提唱されたことがグローバルファンドの発端です。國井局長は、現在、グローバルファンドが支援する国では、「1つの予算、1つの計画、1つの報告」というルールのもと、その国の政府と様々な援助機関やNGO・市民社会が連携して対策を実施しており、グローバルファンドはそのための黒衣として促進・調整役に徹していることを強調しました。
 企業からは、グローバルファンドの民間企業ドナーとしては最長の10年にわたる寄付を行ってきた武田薬品の平手晴彦氏(武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー)が登壇しました。平手氏は、企業の立場から見て、官民連携による途上国への支援が成功する要件として、3点を挙げました。すなわち、(1)長期にわたるコミットメントがあること、(2)持続可能なビジネスモデルであること、(3)その国の主体性を引き出す仕組みを持っていることであり、グローバルファンドはいずれの要件も備えており、かつ投資に対する結果分析のデータが明確に出てくることが素晴らしく、それが企業として共鳴する理由であると説明しました。また、寄付という手法をとることについて、CSRは単発のチャリティ的な寄付であると誤解されることが多いが、中長期のコミットがある寄付であれば、継続性をもった事業の仕組みを作ることができるとし、事実、武田の場合は、複数年の寄付は初年度に全額計上し財政状況に左右されない継続性
企業からは、グローバルファンドの民間企業ドナーとしては最長の10年にわたる寄付を行ってきた武田薬品の平手晴彦氏(武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー)が登壇しました。平手氏は、企業の立場から見て、官民連携による途上国への支援が成功する要件として、3点を挙げました。すなわち、(1)長期にわたるコミットメントがあること、(2)持続可能なビジネスモデルであること、(3)その国の主体性を引き出す仕組みを持っていることであり、グローバルファンドはいずれの要件も備えており、かつ投資に対する結果分析のデータが明確に出てくることが素晴らしく、それが企業として共鳴する理由であると説明しました。また、寄付という手法をとることについて、CSRは単発のチャリティ的な寄付であると誤解されることが多いが、中長期のコミットがある寄付であれば、継続性をもった事業の仕組みを作ることができるとし、事実、武田の場合は、複数年の寄付は初年度に全額計上し財政状況に左右されない継続性
 続いて、マラリア対策の切り札である蚊帳や室内残留スプレーの開発で、世界的な認知を受けている住友化学の石渡多賀男氏(住友化学株式会社生活環境事業部開発部部長)は、グローバルファンドは現在、世界中の蚊帳の購買の約6割に関与し大きな存在感を示しているが、加えて最近では、新製品の市場導入や普及促進プログラムにもグローバルファンドが協力・参画しており、企業の新製品開発のモチベーションを上げる効果があり、大変勇気付けられていると指摘しました。
続いて、マラリア対策の切り札である蚊帳や室内残留スプレーの開発で、世界的な認知を受けている住友化学の石渡多賀男氏(住友化学株式会社生活環境事業部開発部部長)は、グローバルファンドは現在、世界中の蚊帳の購買の約6割に関与し大きな存在感を示しているが、加えて最近では、新製品の市場導入や普及促進プログラムにもグローバルファンドが協力・参画しており、企業の新製品開発のモチベーションを上げる効果があり、大変勇気付けられていると指摘しました。
住友化学は製品開発の分野で多くの国際組織とパートナーシップを組んでいますが、その背景として石渡氏は、感染症対策の商品は市場規模が小さく、また、困っている人に対して低価格で提供するという社会的使命から、製品価格を抑えなければならず個別事業の採算性が低い。その一方で殺虫剤への抵抗性が急速に拡大しているため、絶え間ない新製品開発が要求される。この経済性と技術面での問題のギャップを埋めるためには一企業の努力だけでは限界があり、国際機関等の協力や連携が重要であると訴え、グローバルファンドにはより積極的に新製品の普及に関わってほしいと期待を述べました。
 ジェンダー問題に詳しいジャーナリストの治部れんげ氏は、サハラ以南アフリカでは思春期の女子と若い女性の新規HIV感染が、同世代の男性に比べて圧倒的に高いことに対し、医学の進展にもかかわらず特定の属性において感染が増えている背景には、何らかの脆弱性があり、ジェンダー規範、すなわち女子あるいは男子はこうあるべきという社会の問題があると指摘しました。性交渉や出産における選択権が女性にない、あるいは、半ば強制されたような形で高齢のパートナーとの結婚を強いられ、女性に対する性暴力が社会に受け入れられている現実がある。こういった問題に対して、息の長い取り組みをしてほしいとグローバルファンドへの期待を述べました。
ジェンダー問題に詳しいジャーナリストの治部れんげ氏は、サハラ以南アフリカでは思春期の女子と若い女性の新規HIV感染が、同世代の男性に比べて圧倒的に高いことに対し、医学の進展にもかかわらず特定の属性において感染が増えている背景には、何らかの脆弱性があり、ジェンダー規範、すなわち女子あるいは男子はこうあるべきという社会の問題があると指摘しました。性交渉や出産における選択権が女性にない、あるいは、半ば強制されたような形で高齢のパートナーとの結婚を強いられ、女性に対する性暴力が社会に受け入れられている現実がある。こういった問題に対して、息の長い取り組みをしてほしいとグローバルファンドへの期待を述べました。
治部氏は、ケニアでグローバルファンド支援の事業を取材した経験から、グローバルファンドについて、もっと一般国民の理解を促進していく必要があると指摘し、特にグローバルファンドは資金規模が大きいので、一般読者にはピンとこない。価値を伝えるためにメディアは想像力を掻き立てる記事を書いていかなければならない、と会場にいたメディア関係者を鼓舞しました。
 メディアとともに重要なのが著名人を起用した意識啓発です。蓑輪光浩氏(ビル&メリンダ・ゲイツ財団東京オリンピック・プロジェクト・マネジャー)は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、スポーツ庁、ゲイツ財団が立ち上げたOUR GLOBAL GOALSについて解説しました。これはアスリートを起用してSDGsの認知と理解拡大を目指していくプロジェクトで、グローバルファンドの主目的であるエイズ、マラリア、結核についての優先順位は非常に高いとの説明がなされました。ゲイツ財団が昨年末に行ったSDGsの認知度調査によると、25~34歳の都心部に住む男性、そして55歳以上の一般女性がSDGsや社会貢献に対する意欲が高いという結果が出たそうです。前職まではスポーツ・マーケティング業界に身をおいていた蓑輪氏は、近年は、スポーツ選手の背景も多様化しているので、エイズやマラリア、結核の問題について理解してもらい、発信してもらうことを狙っている。「グローバルファンドは、日本の誇りだ。分かりやすい形でストーリーを発信し共感を広げたい」と抱負を述べました。
メディアとともに重要なのが著名人を起用した意識啓発です。蓑輪光浩氏(ビル&メリンダ・ゲイツ財団東京オリンピック・プロジェクト・マネジャー)は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、スポーツ庁、ゲイツ財団が立ち上げたOUR GLOBAL GOALSについて解説しました。これはアスリートを起用してSDGsの認知と理解拡大を目指していくプロジェクトで、グローバルファンドの主目的であるエイズ、マラリア、結核についての優先順位は非常に高いとの説明がなされました。ゲイツ財団が昨年末に行ったSDGsの認知度調査によると、25~34歳の都心部に住む男性、そして55歳以上の一般女性がSDGsや社会貢献に対する意欲が高いという結果が出たそうです。前職まではスポーツ・マーケティング業界に身をおいていた蓑輪氏は、近年は、スポーツ選手の背景も多様化しているので、エイズやマラリア、結核の問題について理解してもらい、発信してもらうことを狙っている。「グローバルファンドは、日本の誇りだ。分かりやすい形でストーリーを発信し共感を広げたい」と抱負を述べました。
 閉会挨拶で、逢沢一郎衆議院議員(グローバルファンド日本委員会共同議長)は、AU議連の会長としてアフリカの国々を訪問する際には、グローバルファンドの資金が各国でどのように生かされているか自分の目で確認しているが、グローバルファンドはその国の人材を育て、キャパシティ構築に貢献していることを実感する、と述べました。日本の総合力が結集したグローバルファンド日本委員会として、15周年という機会に油断することなく、感染症にしっかりと向き合い、終息させる決意で努力するとともに、日本がグローバルファンドを通じて知見や技術、資源を展開していくことを期待したいと総括しました。
閉会挨拶で、逢沢一郎衆議院議員(グローバルファンド日本委員会共同議長)は、AU議連の会長としてアフリカの国々を訪問する際には、グローバルファンドの資金が各国でどのように生かされているか自分の目で確認しているが、グローバルファンドはその国の人材を育て、キャパシティ構築に貢献していることを実感する、と述べました。日本の総合力が結集したグローバルファンド日本委員会として、15周年という機会に油断することなく、感染症にしっかりと向き合い、終息させる決意で努力するとともに、日本がグローバルファンドを通じて知見や技術、資源を展開していくことを期待したいと総括しました。
 続くレセプションで挨拶した古川元久衆議院議員(グローバルファンド日本委員会共同議長)は、感染症の越境性に触れ、インバウンドの増加や外国人材の受け入れ拡大は、感染症が流行している国からも多くの人が日本を訪れ感染症が国内に持ち込まれる可能性が高くなることを意味し、グローバルファンドに拠出し感染症対策を進めることは途上国の人々の命を救うだけでなく、結局は日本人自身の健康を守ることにつながると、改めてグローバルファンドに拠出する意義を強調しました。
続くレセプションで挨拶した古川元久衆議院議員(グローバルファンド日本委員会共同議長)は、感染症の越境性に触れ、インバウンドの増加や外国人材の受け入れ拡大は、感染症が流行している国からも多くの人が日本を訪れ感染症が国内に持ち込まれる可能性が高くなることを意味し、グローバルファンドに拠出し感染症対策を進めることは途上国の人々の命を救うだけでなく、結局は日本人自身の健康を守ることにつながると、改めてグローバルファンドに拠出する意義を強調しました。
多くの皆様にご参加いただき、本当にありがとうございました。
- グローバルファンド日本委員会15周年記念イベント プログラムと登壇者略歴
- 15周年記念ビデオ
- グローバルファンド日本委員会設立15周年を迎えて (JCIE 執行理事 伊藤聡子)
スピーカー略歴 (登壇順)
大河原 昭夫
(公財)日本国際交流センター理事長、グローバルファンド日本委員会ディレクター
1973年住友商事株式会社入社、海外運輸部、自動車部等を経て1991年よりワシントン事務所次席、1997年より情報調査部にて部長代理、部長を歴任。2004年より(株)住友商事総合研究所に勤務、2006~13年まで同研究所取締役所長を務め、2014年4月より現職。日米文化教育交流会議(カルコン)委員、ベルリン日独センター評議員を兼務する他、日英21世紀委員会日本側ディレクター、日独フォーラム委員、日韓フォーラム幹事委員、国際保健の分野では、グローバルヘルスと人間の安全保障プログラム運営委員会幹事、グローバルファンド 日本委員会ディレクター等を務める。慶應義塾大学法学部卒。
ピーター・サンズ(Peter Sands)
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)事務局長
英国外務省、マッキンゼー・アンド・カンパニーでの勤務を経て、新興国・地域を主なマーケットとする英スタンダード・チャータード銀行グループの最高財務責任者に就任。2006~15年まで同行の最高経営責任者として、事業や利益を拡大し、政府援助を受けず欧州経済危機を回避したことで知られる。任期中、発展途上国の保健に重点を置く同銀行のCSRプログラムを統括し、寄付やロジスティック支援などエイズやマラリア対策に貢献した。その後、グローバルヘルス分野に身を投じ、ハーバード・グローバルヘルス研究所およびハーバード大学ケネディ・スクールのモサヴァー・ラーマニ政治経済センターのリサーチフェローに就任。金融界での豊富な経験を生かしグローバルヘルス財政分野で活躍、2015~16年には、米国医学アカデミーの「グローバルヘルス・リスクフレームワーク委員会」の委員長、2016~17年には、世界銀行の「パンデミックに備えるファイナンスに関する国際ワーキング・グループ」の議長を務めた。2018年3月にグローバルファンド事務局長に就任。オックスフォード大学卒業、ハーバード大学大学院公共経営学修了。
エロイザ(ルイ)・ゼペダ・テン(Eloisa “Louie” Zepeda Teng)
多剤耐性結核を経験した患者代表、アクティビスト
1983年生まれ、フィリピン出身。西太平洋地域の代表としてストップ結核パートナーシップに参画するほか、フィリピン視覚障がい者労働組合の女性委員会のアドボカシー活動にも貢献。2007年に結核に感染、結核性髄膜炎を発症。誤診による発見の遅れと不適切な治療により、多剤耐性結核(MDR-TB)となる。長い闘病生活中、後遺症として視力を失い、うつ病に苦しむ。治療後、アメリカン大学より障がい者政策比較の修士号を取得し、障がい者を含めたすべての人々が結核の治療を受けられるように取り組む。既婚、1女の母。
オマール・シャリフ(Omar Syarif)
世界HIV陽性者ネットワーク(GNP+)コミュニティ開発プログラム・マネージャー
2005年にインドネシアのHIV陽性者の支援グループに加わり、その後ジャカルタ市西部地区で注射薬物使用者のハームリダクションに取り組むNGOのアウトリーチ・ワーカーとなる。2008年には「インドネシア全国HIV陽性者ネットワーク」の立ち上げを支援、同組織の資金調達役に就任。2011~12年には同組織のナショナル・コーディネーターを務め、国内やアジア地域の各種の戦略的プラットフォームにHIV陽性者を代表して参加、インドネシアにおけるグローバルファンド国別調整メカニズム(CCM)や、「国連HIVと移住に関する地域共同イニシアティブ」にも参加する。その後、タイ・バンコクにて「アジア太平洋地域HIV陽性者ネットワーク(APN+)」の能力開発プログラム・マネージャーを務めた後、2017年より「世界HIV陽性者ネットワーク(GNP+)」に参加。現在、GNP+のコミュニティ開発プログラム・マネージャーとしてHIVとC型肝炎治療へのアクセス強化のためのコミュニティグループの提唱力強化に取り組む。
稲場 雅紀
(特活)アフリカ日本協議会国際保健部門ディレクター、(一社)SDGs市民社会ネットワーク業務執行理事
1990年代に横浜・寿町の日雇労働組合での医療・生活相談活動、レズビアン・ゲイの人権課題への取り組みを経て、2002年より(特活)アフリカ日本協議会の国際保健部門ディレクターとしてアフリカのエイズ・保健問題に取り組む。2004年~09年にかけて、途上国のエイズ・結核・マラリア対策に資金を供給する国際機関「グローバルファンド」(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)理事会先進国NGO代表団メンバー。その後、同機関を支援する市民社会ネットワーク「グローバルファンド活動者ネットワーク」(GFAN)アジア太平洋地域理事を務める。一方、2016年にSDGs市民社会ネットワークを設立、業務執行理事としてSDGsの普及や政策提言にも取り組む。
吉田 智子
米国法人日本国際交流センター(JCIE/USA)シニア・プログラムオフィサー
津田塾大学を卒業後、ニューヨーク大学教育学大学院にて国際地域保健教育学で修士号を取得。カンボジアでのインターンシップを経てサンスターに入社し、企業広報・CSR(企業の社会的責任)を担当した。東日本大震災を契機に日本コカ・コーラに移り、同社および財団にて全国に展開する各種教育プログラムや復興支援活動の企画運営を行う。一方で、学生時代からHIV/AIDSの社会運動に関わり、日本の若者と職場を対象にする啓発活動や全国キャンペーンのテーマ選定に携わる。現在、エイズ予防財団のNGO助成金審査委員を務める。
國井 修
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)戦略・投資・効果局長
1988年自治医科大学卒。医師、公衆衛生学修士、医学博士。内科医として大学病院等で勤務後、僻地医療に従事、また緊急医療のNGOであるAMDAの副代表として、難民への医療援助に従事した。ハーバード大学公衆衛生大学院留学を経て、自治医科大学衛生学助手、国立国際医療センター国際医療協力局厚生技官、日本国際協力機構(JICA)東北ブラジル公衆衛生プロジェクト長期専門家、東京大学国際地域保健学講師を歴任。2001~04年には、外務省調査計画課に勤務し、沖縄感染症イニシアティブの監理・運営のアドバイザーを務めた。この間、世界エイズ・結核・マラリア対策基金の設立にも関与した。2004年より長崎大学熱帯医学研究所教授、2006年よりUNICEFに勤務し、本部にて保健戦略上級アドバイザー、ミャンマー事務所保健・栄養チーフ、ソマリア事務所保健・栄養・水衛生支援事業部長等を歴任した。2013年3月より現職。
平手 晴彦
武田薬品工業株式会コーポレート・オフィサー
慶応大学経済学部を卒業。日製産業、ドレーゲル社アジア代表、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役、米国メルク社、万有製薬の代表取締役社長、グラクソ・スミスクライン社代表取締役専務を経て、2010年に武田薬品工業にコーポレート・オフィサーとして入社。 中国事業の再構築をなした後に、現在は本社機能の国際化を目指し、対外折衝等を統括する。
日本の製薬業界では知名度が高く、日本製薬団体連合会(FPMAJ) の役員、米国研究製薬工業協会(PhRMA) 日本代表を歴任。現在は、経済同友会の幹事、日本製薬工業協会(JPMA) の国際委員会委員長を務める。
蓑輪 光浩
ビル&メリンダ・ゲイツ財団東京オリンピックプロジェクトマネージャー
スポーツマーケティングにおいて20年超の経験を持つ。1997年に中央大学を卒業後、NIKE入社。主にデジタル コミュニケーションをリードし、ワールドカップ、オリンピック、箱根駅伝、NIKEiDをはじめとした様々なプロジェクトに従事。グッドデザイン賞、カンヌ広告賞を多数受賞。2008年よりNIKE EUROPEに赴任し、ヨーロッパにおけるeコマース展開拡大とデジタル マーケティングを手がける。2011年よりユニクロに入社し、錦織圭、ジョコビッチらトップアスリートの契約、PR広告戦略、イベント、スポーツ商品開発に携わる。2016年よりレッドブルに入社し、300人超のチームを率い、エアレースやF1など年間500のイベントやマーケティング活動を展開。2018年にビル&メリンダ・ゲイツ財団に加わり、東京オリンピック プロジェクトマネージャー就任。
石渡 多賀男
住友化学株式会社 生活環境事業部 開発部 部長
1988年、東京大学大学院修士課程修了(応用昆虫学専攻)。同年4月住友化学に入社、研究所および本社勤務を通じ一貫して家庭用、防疫用殺虫剤の研究、開発、技術普及に従事。WHO(世界保健機関)から世界で最初に推奨を受けたマラリア防除用の長期残効蚊帳(LLIN)「オリセットネット」、殺虫剤抵抗性マラリア媒介蚊への効力を増強した新規LLIN「オリセットプラス」、同じく殺虫剤抵抗性マラリア媒介蚊に高い効力を有する室内残留散布剤「スミシールド」、デング熱などの感染症予防に有効な長期残効型の蚊発生源処理剤「スミラブ®2MR」等の研究開発に取り組む。2015年より現職。
治部 れんげ
ジャーナリスト、W20日本2019運営委員会委員、(公財)ジョイセフ理事
1997年、一橋大学法学部卒。日経BP社にて経済誌記者。2006~07年、ミシガン大学フルブライト客員研究員。2014年よりフリージャーナリスト。2018年、一橋大学経営学修士課程修了。日経DUAL、Yahoo!ニュース個人、東洋経済オンライン、Business Insider等にダイバーシティ経営、男女のワークライフバランス、ジェンダー平等教育について執筆。現在、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。東京大学大学院情報学環客員研究員。日本政府主催の国際女性会議WAW!国内アドバイザー。東京都男女平等参画審議会委員(第5期)。2019年、日本が議長国を務めるG20に政策提言する女性グループW20運営委員。公益財団法人ジョイセフ理事。一般財団法人女性労働協会評議員。著書に『炎上しない企業情報発信:ジェンダーはビジネスの新教養である』(日本経済新聞出版社)、『稼ぐ妻 育てる夫:夫婦の戦略的役割交換』(勁草書房)等。2児の母。
伊藤 聡子
(公財)日本国際交流センター執行理事、チーフ・プログラム・オフィサー、グローバルファンド日本委員会事務局長
慶応義塾大学卒、ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)修士課程修了。民間企業を経て1988年より日本国際交流センター勤務。民間非営利セクターの基盤整備や企業市民活動促進のための諸事業に従事し、1997~2004年までリーバイ・ストラウス・コミュニティ活動推進基金による助成プログラムを担当、日本国内のHIV/エイズ、移民問題等の社会正義分野のNPO支援を専門とした。2004年以降、国際保健分野の事業に従事。グローバルファンド日本委員会には立ち上げから関わったほか、「グローバルヘルスと人間の安全保障プログラム」、「アジアの高齢化と地域内協力」など、JCIEのグローバルヘルス関連の諸事業を統括する。
逢沢 一郎
衆議院議員、グローバルファンド日本委員会アドバイザリー・ボード共同議長
(略歴掲載準備中)
古川 元久
衆議院議員、グローバルファンド日本委員会アドバイザリー・ボード共同議長
(略歴掲載準備中)