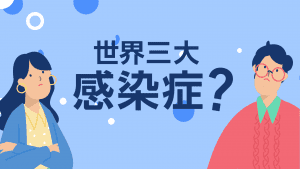日本ODAの着実な成果を、グローバルファンドで国全体に広げる
インタビュー
野崎 威功真氏
(国立国際医療研究センター(NCGM)国際医療協力局医師、国際協力機構(JICA)カンボジア保健政策アドバイザー、グローバルファンド技術審査委員会(TRP)メンバー)
JICAのHIV専門家として、アフリカや東南アジアでの保健対策に豊富な経験をもち、現在もカンボジアで保健政策アドバイザーを務める野崎威功真さん。お父さまもミャンマーにかかわるJICAの専門家で、幼少期から国際協力を間近に見てきましたが、その足跡は一本道ではなかったようです。ご経歴や支援国での経験、また日本のODAの特徴や今後の課題などについて、たっぷりとお話しを伺いました。
合格学生時代、ワークキャンプで出会った國井修先生に憧れた
― きょうはカンボジアとオンラインでつないで、お話しをうかがいます。
2022年5月までは、カンボジアの保健省で母子保健プロジェクトのチーフアドバイザーを政策アドバイザーとの併任でやっていました。日本は、カンボジア内戦が終わった直後から国立母子保健センターを建て、技術支援を続けています。おかげでカンボジアは、ミレニアム開発目標のうち母子保健の目標指数を達成した数少ない国です。母親や5歳未満児の死亡が減ってきたところで、つぎの課題として、赤ちゃんが死なないようにというプロジェクトに取り組んできました。
ぼくがこちらへ来たのは2020年10月のコロナ真っ只中で、医療従事者の研修など対面活動が難しく、オンライン教材を作ったりしました。また地域ごとにコミュニティに密着した医療機関としてヘルスセンターが置かれていますが、センタースタッフの孤立を回避するためのアプリを開発したり、自学教材を作ったりしていました。
カンボジアへ赴任するまえは、ミャンマーの感染症対策にかかわっていました。

― お父さまもアジア学院(栃木県)などに勤めて、国際協力の専門家でいらしたそうですね。
小学校からは那須へ移っていましたが、父の仕事の関係でミャンマーに2年いたこともあります。父もJICAの専門家で、親子でミャンマーにかかわるJICAの専門家って、珍しくないですか?(笑)
小さいときは、国際協力の仕事についてよく理解できてはいなかったです。家もそれほど裕福ではなかったし、外国人が子ども心に怖かったりして、将来、自分がそれに取り組むとは思っていませんでした。ただ、父が引率するインドネシアでのワークキャンプに大学1年のときに参加し、インドネシアの地方都市で土木作業などを手伝いました。役に立てると意気込んで行ったものの、学生ができることなんて知れていて、いちばんいいところに泊まり、いい食事をして、それで土運びなどの単純作業。自分はなんの役に立っているのだろう、と意気消沈しました。
そのとき医療班で来られていたなかに、國井修先生(前グローバルファンド戦略・投資・効果局長)がいらっしゃいました。まだ研修医か駆け出しのころだったと思いますが、見ていて颯爽として、かっこいいわけです(笑)。自分もだれかに貢献しようと思ったら、なにか“武器”をもたないとダメだと思いました。ぼくはミッション系の高校に進学し、その推薦枠で同志社大学の工学部になんとなく進学したのですが、その後もネパールでのキャンプに参加するうち、開発の仕事をしようと思い立ち、卒業後、医学部を受け直すと決めました。

― あらためて信州大学の医学部に進まれました。
うちの影響でぼくもクリスチャンなのですが、大学に日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)の活動をしている先輩がいて、ぼくも臨床の仕事で海外協力したいというイメージをもちました。JOCSは海外へ医者を送ったりしていたので、そういう現地の医師を訪ねて、バングラディシュやネパール、カンボジアにも行ってみました。

信大はユニークで、5回生のとき3か月間自由に過ごしていい期間があり、ぼくも研究室に所属させてもらって、夏休みとあわせた期間、ネパールに行き、そのとき開発の仕事をしようと心を決めたんです。


国立国際医療研究センターや新宿の多様な患者さんが出発点となる
― ご卒業後は小児科を選ばれました。
在学中はJOCSの活動をし、卒業時にいくつか声もかけていただいたのですが、国際医療センター(現・国立国際医療研究センター)に知っている先輩がいたのでそちらに決めました。小児科を選んだのは、国際協力では内科、外科、産科などメジャーに携わりたいと思ったなかで、ネパールなど子どもの死亡率が高い現実に接して子どもへの関心があったことと、外科は現地に施設も少ないし、やはりぼくが医学部入学まで5年遠回りしていたので、一人前になるのに時間がかかるイメージがあり、小児科を選びました。
学生時代は、大学病院へ来る子は困難な状況にあることが多いですから、小児科実習は少し辛かったですね。ただ市中病院での実習では、きのうぐったりしていた子がきょう走り回ったりするのが嬉しくて。あと、国際医療センターのエイズ治療・研究開発センター病院はHIV診療で知られますが、医療センターの小児科では母子感染の子どもの陽性者さんも診ていました。ぼくはのちにHIVの専門家として国際協力に携わりますが、国際医療センターでのHIV診療や、新宿という土地柄からさまざまな国籍や社会的背景をもつ多様な患者さんに接した経験は、その後の出発点ともなり、ぼくの強みとなったと思います。

― HIVを診るうえで、ゲイの人と接することは当たり前ですからね。
小児科なので直接、成人のゲイ男性のかたを診る機会はなかったですが、外国現地で活動すると、性的マイノリティの人への差別偏見はそうとう厳しく、難しさを感じました。また、キリスト教徒のなかに性的マイノリティに否定的な人がいることも知ってはいますが、ぼく自身はそういうことにはこだわらないでこれました。
そうそう、のちにハーバード大学(ボストン)に留学させてもらったとき、子どもを地域校に通わせて、アメリカはおもしろいなと思ったことがあります。娘の担任がゲイの人で、そのパートナーがアシスタントティーチャーで、娘は「先生どうし結婚してんだよ」と普通に見ていて、こういう環境で育つといろいろ違うな、親以上にダイバーシティーにオープンマインドなんだな、と思いました。途上国だとまだ権威主義的だったり、マイノリティへの嫌悪感が障壁になることがありますね。
現実との折り合いの難しさに直面する途上国支援
― これまでの赴任先でのお仕事について、教えてください。
ザンビア共和国には2007年に、HIV専門家として行きました。3×5(スリーバイファイブ)イニシアチブ(300万人を2005年までに治療するという方針。2003年採択)のもとで治療は始まっていましたが、限られた施設でのことでした。その当時、ザンビアのHIV感染率が17%ぐらいですが、ザンビアは都市化率が高くなく、国土の各地に人が分散して住んでいる感じです。都市部にしか治療所がなく、治療の継続が難しいのです。人が住むコミュニティの近くにまで治療を広げないといけない。
しかし、ザンビアは英連邦加盟国で、医師免許が連邦圏全体に通じます。全国で1つしかない医学部の定員が50名ですが、卒業生の半分が海外に行ってしまう。医師が全国で700人しかいない状況でした。72郡あり国土面積が日本の2倍ですから、1郡が日本の1県ぐらいの感覚で、そこに医師が1人か2人なのです。
HIVは、途上国がはじめて経験する慢性疾患といえます。それまでは肺炎など、急性期治療が生死を分ける病気の対策しか取り組んだことがない。それが初めて定期的な受診と服薬を継続する体制をつくらなくちゃいけなくなった。医者もいない地方の都市でできるのか。それでモバイルクリニックという、郡の病院を基地に地域のヘルスセンターを医師が巡回する体制をつくりました。

もっとも、この巡回診療は各国から来た支援NGOが地域単位で運営するのはよく見られるのですが、そのNGOが帰国するとあとに残らない。ぼくらはある郡で、ヘルスセンターの現地スタッフが治療を提供し、医師が巡回してそれをサポートする体制をつくる手伝いをし、治療効果をあげることができました。そのモデルをグローバルファンドの資金で他の郡にも広げることになり、その後任で来たのが、すでにこのコーナーでインタビューされた宮野医師(記事はこちら)。病院でもぼくの後輩にあたります。


― 支援国での難しさには、どんなことがありますか。
アフリカでHIVは、セックスコネクションを多くもつ層、ありていにいえば社会的高位や富裕者など、社会の根幹である人たちの病気であるのも事実です。女子生徒のセクシュアルデビューが学校教師というのもよく聞く話で、教師層にも陽性者が多い。そのことを道徳的・倫理的に嫌悪するのは自由ですが、HIVは人間の弱い部分をついて広がるというと語弊がありますが、それがウィルスの戦略。聖人君子の世界を想定しても対策はうまくいきません。
同性愛やMSM(Men who have sex with men: 男性と性行為をする男性のこと)の人を否定している社会でも、対策はうまくいかない。本当に必要な人にサービスが届かないし、ターゲットグループが潜伏するだけです。このあと赴任したミャンマーでは、軍政下、「強い軍にHIVなど“いかがわしい”病気はない」という建前で、国の公式統計でHIV陽性者はゼロであった時期があったと聞きました。またコンドームを持ち歩いていることが売春の証拠にされ、摘発されるので、せっかく配っても携行してもらえない。そういう限界のなかで、できることを進めていかなくてはいかない。現実との折り合いの難しさを感じました。
きめ細かい対応で着実な実績をあげる日本式ODA
― ミャンマーではどういうお仕事を進めたのでしょう。
ミャンマー赴任は2013年、軍政時代で、世界から制裁を受けていたため支援にも限界がありました。ただ日本は戦後賠償のからみもあって政府開発援助(ODA)を続け、保健分野は人道主義の面からも長く続けていました。エイズ、結核、マラリアと、性格も対策も違う病気ですが、それぞれに支援プログラムを組むと見かけ上数が増えるので、むりやり一つにまとめたり(笑)。
国情から、MSMやセックスワーカーの人たちに近接しての予防啓発は難しく、グローバルファンドによる治療支援も止められて、私たちは輸血を介した感染の防止支援にとどめざるをえませんでした。
ミャンマーは「ゴールデントライアングル」(麻薬密造地として知られた国境山岳地帯)も近いせいかドラッグユーザーの問題が深刻で、ホットスポットになっていました。一方、血液バンクの制度がなく、輸血が必要なときには患者側が人を集めたり、病院前で献血しようと待っている人にお願いするわけですが、感染症のリスクも高い。そのなかにはドラッグユーザーの人などもいるわけです。実際、そうしたグループのHIV陽性率は、一般国民に占める割合より高いくらいでした。もちろん血液の検査はしますが、ウィンドウピリオド(感染後、一定期間ウイルスを検知できない空白期のこと)をくぐり抜けるものもある。
日本のように多くの人が自発的に献血する仕組みができればと思い、仏教の喜捨文化もあり、お坊さんの支援などを受けながら体制づくりを支援しました。保健省の輸血部門の担当だった方が献身的に取り組まれたことは、いまも強く記憶に残っています。高官にもかかわらず社会の各層と気さくにつきあい、スーパーマーケットから献血者への軽食を寄付してもらったり、ビジネス界からも寄付をしてもらったり。高官である彼女の呼びかけで、ある高僧のかたがサポートしてくれ、コミュニティの信頼が得られ、献血者が増えていったそうです。自発的献血が増えるにつれ、HIV陽性の割合もどんどん下がっていきました。彼女とは、私がカンボジアに赴任したいまでも親交があります。


― 結核やマラリアにも取り組まれますね。
HIVと結核、マラリアの3つの疾患の対策を支援するプロジェクトのチーフアドバイザーをしていましたので。結核は貧困層のかたに多い病気で、スラム街などで感染も広がりやすく、体調が悪くても仕事も休めない。近所の薬局とも呼べないような売店で買った薬を飲み、さらに悪くなることが多かったのです。それでまずそうした薬局のトレーニングをやり、いろんなかたちで患者を早く発見し、治療に乗せる取り組みなどを支援しました。
マラリアでは、アフリカの場合は都市にも多いのですが、アジアのマラリアは山間の森林部に多い。山に入る仕事の人に広がっていて、診断も治療も届きづらい。ボランティアを養成し、その人たちに診断キットを持たせて現地へ入ってもらい、陽性なら治療する体制をとりました。保健システムが届かない先への対策を経験させてもらいました。
マラリアにつきものの蚊帳の配布もそうで、つい配りやすいところしか配られず、都市の周りで何度も配られたりするのです。それで行政区画単位でなく、マイクロプランニングというのですが、この村には何人いて、蚊帳が何張必要、と細かく把握して配りました。この方式はあとでユニセフにも受け継がれたと聞いています。現地の人とのネットワークが必要ですね。
グローバルファンドは大きな資金で広い面をカバーする一方、日本のODAは広い地域は難しくても、細かい対応に特色があります。ミャンマーでのODA活動も二つの州でしか実施できませんでしたが、それをグローバルファンドのお金で政府が全国に広げる際のモデルになりました。


豊富な現場経験から「出口戦略」を展望
― 豊富な現場経験を買われて、グローバルファンドの技術審査員をお勤めです。
2020年の8月からHIVの専門家として拝命し、結核専門の宮野さんと同時に勤めています。ぼくらはすでにオンライン審査の世代ですが、資料を読む量は少なくはないですよ(笑)。
審査の詳細はお話することができませんが、自分としてむずかしかったのは、線引きですかね。ここが申請書の課題だと指摘することはできても、申請者へ差し戻すかどうかが難しい。パーフェクトな申請書はないなか、差し戻せばそれだけプロジェクトの開始も遅れます。
審査では、JICAの専門家として日本のODAにかかわり、現場と政策の両方を見てきたことが役立ったと思います。海外の組織では、政策は政策、現場は現場と、分業が多いのです。厚労省に出向した時期、WHO総会など上の階層の様子も見る機会がありましたが、グローバルファンドも同様にグローバルな世界を知る機会となり、建前的なことだけでない話も聞こえてきます。国際会議の出席者は保健の専門家というよりむしろ外交官であって、外交や駆け引き的な部分もあります。
ですが、ぼくはザンビアでもミャンマーでも、現場を歩きながら政府担当者ともいっしょに仕事をしたり議論する経験をもてました。それがおもしろさでもあり強みでもあると思ってきました。そういうことが、審査にも生きていたのではないでしょうか。
― グローバルファンドの果たすべき役割、またご自分にとっての意味を振り返っていかがでしょうか。
2000年代からHIV対策にかかわってきた身として、グローバルファンドが果たしてきた役割は非常に大きいと思います。
ザンビアで活動してきたとき、もともとのプロジェクトデザインは、患者を早く見つけ、早く治療につなぐ、でした。でも、ザンビアでは患者さんを見つけることはもはや課題ではなかった。感染率が平均17%、女性は20%、5人に声をかければ1人は見つかる。むしろその人たちの治療をどうするのかが喫緊だったのです。
先に述べたように、アフリカでの男性感染者は社会の上位・中心を占める層に多く見られ、もし治療がなく、その人たちが10年後にごっそりいなくなったとしたら、国は社会体制を維持できただろうか。少なくともいまこうして国が体(てい)をなしているだけでも、グローバルファンドがアフリカの国に果たした役割は大きかったといえます。
今後の課題は出口戦略だと思います。急性期は過ぎた、国によっては—-とくにアジアでは—-急性期を卒業し、自国の保健制度のなかで治療もできるようになった。そういう国が少しでも増え、自国の医療保険で治療がまかなえる世界を目指すための支援が必要です。緊急医療じゃなく、いまある既存の医療体制に、エイズ、マラリア、結核の3疾患治療を組み込んでいく体制づくりを目指さないと、毎回増資サイクルのたびに金額を積み増すだけでは、いつかもたなくなるのは目に見えています。今後のビジョンが必要ですね。
HIVの感染終息に向けて、「3つの90」などの目標が言われていますが、いかに現地国のシステムに落とし込み、定着させるか。日本国内に困っている人がいるのに海外なんて、とODAに厳しい目が向けられる現状もあります。しかし、SDGs目標が掲げられ、国内を含めた持続可能な未来を考えたとき、日本も変わるための援助と位置付け、その文脈のなかで3疾患のこともとらえてほしいですね。難しいものですが。でも、そうやって、いつかグローバルファンドがいらない世界を目指さないといけません。
インタビュアー
FGFJ レポート編集協力エディター
永易 至文
*インタビューは2022 年11月にオンラインで実施しました。
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
BACK NUMBER
グローバルファンド日本委員会(FGFJ)では、グローバルファンドと何らかの関わりのある日本人をインタビューし、「日本人(わたし)とグローバルファンド」というコラムでウェブサイトに掲載しています。バックナンバーはこちらのページからご覧ください。